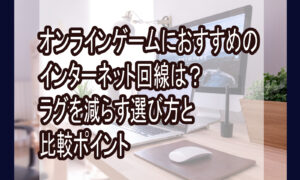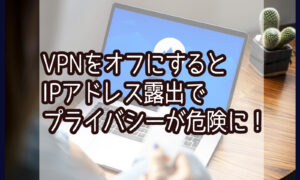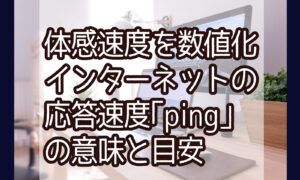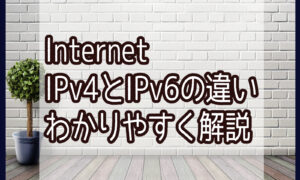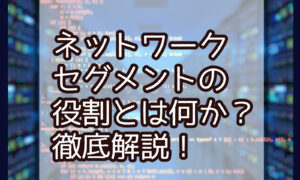SNS時代に求められる「言葉のリテラシー」
インターネットやSNSが普及した現代では、誰でも自由に意見を発信できる一方で、「それ、言い過ぎじゃない?」という投稿が目立つようになりました。
正当な批判と誹謗中傷は、時に線引きが曖昧で、知らないうちに加害者や被害者になっていることもあります。
本記事では、誹謗中傷と正当な批判の違いをわかりやすく解説し、境界線の見分け方や対処法も紹介します。
ネットを安全・安心に使うための参考にしてください。
【1】誹謗中傷と正当な批判の違いとは?
◆ 誹謗中傷とは?
誹謗中傷とは、根拠なく他人を傷つける言動のことです。特に以下のような特徴があります。
- 事実に基づかない悪口
- 感情的な侮辱や暴言
- 個人情報の晒し、名誉毀損につながる内容
例)「あいつは頭がおかしい」「〇ね」「顔が気持ち悪い」
◆ 正当な批判とは?
正当な批判は、事実や論拠に基づいて意見を述べる行為です。目的は「指摘」や「改善提案」であり、以下のような特徴があります。
- 相手の行動や発言にフォーカスしている
- 感情ではなく論理的な表現
- 相手の人格を否定しない
例)「この発言は誤解を招くので、情報源を明示すべきです」
【2】線引きのポイントは「目的」と「言い方」
批判が誹謗中傷に変わるのは、伝える目的と表現方法にあります。
| 判別基準 | 誹謗中傷 | 正当な批判 |
|---|---|---|
| 根拠 | 感情・憶測 | 事実・データ |
| 目的 | 相手を傷つける | 問題点を指摘する |
| 表現 | 侮辱・暴言 | 丁寧・冷静な言葉 |
| 焦点 | 相手の人格 | 発言や行動の内容 |
批判は政党であればしてもいい。けれど、人格攻撃はNG。
これが大きな境界線です。
【3】誹謗中傷を受けたときの対処法
万が一、SNSや掲示板で誹謗中傷を受けた場合は、感情的に反応せず、冷静に対処しましょう。
スクリーンショットを保存する
削除される前に、証拠として投稿内容・アカウント情報を記録しておくことが重要です。
プラットフォームに通報・ブロックする
XやInstagram、YouTubeなどはガイドライン違反の通報機能が整備されています。速やかに対応を。
法的措置を検討する
名誉毀損や侮辱罪に該当する場合、弁護士への相談や発信者情報開示請求が可能です。専門機関のサポートを活用しましょう。
【4】誹謗中傷を「しない」「させない」ために私たちができること
情報に対するリテラシーを高める
→ 感情的にならず、事実確認を意識する
言葉を選ぶ
→ 相手がどう感じるかを想像しながら投稿する
見て見ぬふりをしない
→ 誹謗中傷が横行する場を放置せず、通報や注意喚起を行う
「自由な言論」と「人を傷つけない配慮」は両立できます。
まとめ|そのコメント、大丈夫?ネットで問われる“人としてのマナー”
誹謗中傷と正当な批判の線引きは、目的・表現・根拠の有無で見分けることができます。
もし誹謗中傷を見かけたり受けたりしたときは、冷静に対処し、必要ならば専門家に相談しましょう。
あなたの言葉が、誰かを守ることも、誰かを傷つけることもある。
ネット社会に生きる私たちにとって、思いやりと言葉の選び方は今まで以上に大切になっています。